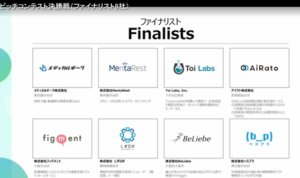m3.comで掲載された執筆記事を公開します。医師の方は下記URLからお読みください。
胸水の原因疾患を特定する機械学習モデルの限界 | m3.com AI Lab
医療DXに関わるニュースや論文に寄せられた医師からの率直なコメントを紹介します。
対象のニュース
年齢、ADA、LDHのみから胸水の原因疾患を特定する機械学習モデル | m3.com AI Lab
胸水はさまざまな疾患によって引き起こされる可能性があり、その鑑別は多岐にわたる。胸水の原因疾患を特定するための機械学習モデルが開発されているが、大半のモデルでは10個以上の特徴量の入力が必要であり、これが検査費用の増加につながっている。(後略)
このニュースに着目した理由
臨床現場では様々な原因による胸水貯留の患者の診療を行う機会がある。胸水の原因疾患の特定のためには胸腔穿刺が必要である一方、これが侵襲的処置であることや、胸水が少量の場合や出血リスクの高い患者への穿刺リスクが高いため行いにくいなどの課題がある。
こういった背景のもと、胸水診断において機械学習モデルがどこまで診断の一助となるのか興味深いと考えこのニュースに着目した。
私の見解
これまでも胸水の原因疾患を特定するための機械学習モデルが開発されてきたが、大半のモデルは10個以上の指標が必要であり、検査費用の増加が課題だった。
今回のモデルでは年齢、胸水ADA、胸水LDHによる分類が可能という点でこれまでのモデルとの差別化を明らかにしている。しかしながら、臨床現場においては、胸腔穿刺を施行すればその検査項目数はそれほど限定するメリットを感じない。
コストの問題は確かに少ない方が良い一方で、正確な診断の方が優先されると考える。そういう点で考えると、あくまで研究的視点では興味深い。一方、臨床現場で導入するメリットはそれほど感じられないのは残念な印象である。
日常臨床への生かし方
臨床現場の視点では、機械学習モデルを使用することで例えば胸水穿刺を行わなくても、胸水以外の血液検体や画像検査などで診断の一助になるというようなモデルが望まれる。機械学習モデルありきという研究では臨床現場で使用されなくなってしまうため、このようなモデルを構築する際は、現場の課題感をしっかり掘り下げた上で開発に生かしてほしいと感じる。